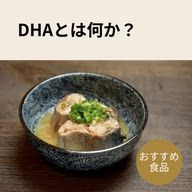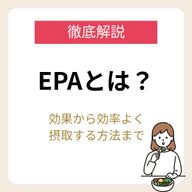2025-11-21
認知症の種類とは?アルツハイマー型・レビー小体型など4大認知症の違いと対応

認知症とひと口に言っても、その種類によって症状や対応方法は大きく異なります。
認知症の種類を正しく知ることが、適切なサポートの第一歩となるでしょう。
そこで今回は、代表的な認知症の特徴や違いをわかりやすく解説し、早期発見や日常生活での接し方の参考になる情報をまとめています。ご家族やご自身の備えとして、ぜひ参考にしてみてください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
岩城 裕大
認知症とは?

認知症とは、脳の障害によって記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす進行性の病気です。
加齢に伴うもの忘れとは異なり、体験自体をすっかり忘れていたり、自覚がないまま同じ質問を繰り返したりする傾向が見られます。
たとえば、食事を済ませた直後にもかかわらず「まだ食べていない」と訴えたり、慣れた道で迷ってしまったりする場面がその一例です。
以下の表では、加齢によるもの忘れと認知症の違いを簡単に整理しています。
| 比較項目 | 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ |
|---|---|---|
| 忘れ方 | 一部を忘れるが思い出せる | 体験全体を忘れ思い出せない |
| 自覚の有無 | 忘れたことを自覚している | 忘れたことを自覚できない |
| 生活への影響 | ほとんどない | 徐々に生活に支障をきたす |
認知症の主な種類

認知症にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や現れ方が異なります。
<代表的な認知症の種類と割合>
- 1アルツハイマー型認知症:67.6%
- 2血管性認知症:19.5%
- 3レビー小体型認知症:4.3%
- 4前頭側頭型認知症:1.0%
ここからは、代表的な4つの認知症について詳しく紹介します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、最も多く見られる認知症の一種です。脳内にアミロイドβやタウタンパクが蓄積し、それによって神経細胞が損傷を受け、ゆるやかに脳の萎縮が進行していきます。
初期には「最近の出来事を忘れる」といった短期記憶の低下が目立つ傾向です。やがて、時間や場所の感覚が曖昧になる「見当識障害」や、料理や買い物といった日常的な段取りが難しくなる「実行機能障害」が現れます。
進行すると、家族の顔を認識できなくなったり、言葉が出にくくなったりするほか、排泄や食事にも全面的な介助が必要となる場面が増えていきます。このように、生活への影響は少しずつ広がっていくのが特徴です。
血管性認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって生じる認知症の一種です。発症は突然のケースもあり、脳卒中をきっかけに急に症状が現れることがあります。
また、障害を受けた脳の部位によって症状の出方が異なることや、「今日は話せたのに明日は反応がない」といったような、できるときとできないときの差が見られやすいのが特徴です。
さらに、記憶力の低下に加えて、以下のような症状が現れることがあります。
- 1手足の麻痺
- 2言葉が出にくくなる(構音障害や発語低下)
- 3突然泣き出す、または表情が乏しくなるなどの情動変化
- 4うつ状態、無気力、意欲低下
血管性認知症では、症状が「階段状」に進行する傾向があります。脳血管障害を再び起こすことで、認知機能が急激に悪化するリスクもあるため、小さな変化でも見逃さず、早めに医師に相談するようにしましょう。
レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、早期発見と見守りが重要な認知症の一種です。脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質が蓄積することで発症し、認知症全体の中でも3番目に多いタイプとされています。
このタイプでは、日によって認知機能の調子に波が見られるほか、実在しない人や虫が見える「幻視」、動きが鈍くなる「パーキンソン症状」などが生じます。
睡眠中の異常行動や便秘、立ちくらみといった症状も特徴です。会話ができる日がある一方で、急に反応が鈍くなることもあります。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が徐々に萎縮し、人格や行動に変化が現れるタイプの認知症です。発症は50〜60代が中心で、初期には記憶の低下が目立たず、以下のような行動が現れることがあります。
- 1万引きや信号無視のようなルール違反
- 2暴言、共感の欠如、無関心
- 3同じ行動を繰り返す、こだわりが強くなる
- 4身だしなみに気を使わなくなる
本人に自覚がないため、異変に気づく家族の存在がとても重要です。記憶力が比較的保たれる初期段階で見分けられることもあり、早めの受診が判断の助けとなるでしょう。
認知症における早期対応の重要性

認知症は進行性の病気ですが、早めに気づくことで将来の選択肢が広がります。
初期段階で受診すれば、生活習慣の見直しや治療によって、進行を遅らせることも期待できます。なかには、正常圧水頭症や甲状腺機能低下症など、治療によって改善が見込める場合もあるでしょう。
加えて、本人の意思を尊重しながら介護サービスや生活環境を整える時間的な余裕も得られます。
認知症のタイプによって接し方やケアの内容も異なるため、日常の言動に違和感を覚えたら、早めに専門機関へ相談することが重要です。
脳の健康を守るためにできること

年齢を重ねても自分らしく暮らしていくためには、脳の健康を意識した生活習慣が欠かせません。食事や睡眠、運動などの積み重ねが、記憶力や判断力を保つ土台となります。
ここでは、脳の健康を守るための方法について解説します。
食事とサプリで脳に必要な栄養素を補う
脳の働きを保つには、毎日の食事が土台になります。
脳の健康を支える栄養素には、次のようなものがあります。
- 1DHA・EPA:青魚や魚油サプリに含まれ、記憶力維持を助ける
- 2ビタミンB群:豚肉や玄米に多く、神経伝達の働きを整える
- 3ビタミンEなどの抗酸化成分:ナッツ類や植物油が豊富で、老化の進行を防ぐ
なかでも、DHAやEPAといった脂肪酸は、記憶力や集中力をサポートする重要な成分です。
青魚に多く含まれていますが、食生活だけでは十分に摂れないこともあるため、サプリメントでの補給も検討するとよいでしょう。
20種類以上の栄養をまとめて摂れるサプリ「Rimenba(リメンバ)」

「最近、ちょっとした物忘れが増えた気がする」
そう感じたときは、脳の栄養状態を見直すタイミングかもしれません。
Rimenba(リメンバ)は、DHA・EPAやプラズマローゲン、葉酸、ビタミンB群など、脳の健康維持に役立つ成分を一度に摂取できるオールインワンサプリです。

1日4粒で20種類以上の栄養素を効率的に補えるため、忙しい方でも無理なく続けやすく、食生活が不規則になりがちな人にも心強い存在となります。
特に注目すべきは、以下のような成分の働きです。
- 1DHA・EPAが含まれており、記憶力や集中力の維持をサポート
- 2認知機能の健やかさを保つ上で期待される成分であるプラズマローゲンも摂取できる
- 3葉酸やビタミンB6・B12も含まれており、神経機能をサポートする
- 4イチョウ葉エキスには、脳の血流を促進し、思考をクリアに保つ働きがあるとされている
脳神経内科医が監修している点も信頼できるポイントです。「うっかり」が気になりはじめたときや、将来の備えとしてぜひお試しください。

Rimenbaは調剤薬局でも取り扱いがありますが、公式サイトなら初回限定の特別価格で購入可能です。詳しくは以下のバナーからチェックしてみてください。
スマホの使いすぎを防ぐ
スマートフォンの長時間使用は、脳に負担をかける要因の1つです。特に就寝前の操作は睡眠の質を低下させ、脳の回復を妨げるとされています。
さらに、次々と表示される情報にさらされることで、集中力や記憶力が低下しやすくなる点も見逃せません。
こうした影響を和らげるには、スマホとの関わり方を見直すことが大切です。たとえば、次のような習慣を取り入れるだけでも、脳をリセットする時間を確保しやすくなります。
- 1就寝1時間前からスマホを見ないようにする
- 2食事中は画面を伏せて、目や手を離しておく
- 3操作の目的が曖昧なときは、意識的に手を止めるようにする
このような工夫によって、脳に休息の余白が生まれ、思考力や集中力の回復も期待できます。
脳を活性化させる運動と習慣を日常に取り入れる

運動や生活習慣の見直しは、年齢を重ねた脳の働きを守るための効果的な方法とされています。特に有酸素運動は、脳への血流を促進し、記憶力や集中力の維持に効果があるといわれています。
また、気分が前向きになることで、日常の過ごし方にもよい影響をもたらすでしょう。
無理なく続けられる範囲で構いませんので、脳の健康を意識した以下のような行動を少しずつ取り入れてみてください。
- 1ウォーキングを習慣化し、気分転換と血流促進を両立させる
- 2興味のある本や趣味を通じて、知的な刺激を得る
- 3家族や知人との会話を増やし、感情や思考のやりとりを意識する
- 4食事の際によく噛むことで、脳の活性化と集中力の向上を図る
睡眠環境を整えて、脳の疲労を回復させる
質の高い睡眠は、脳の記憶定着を助け、老廃物の排出にも関与するとされています。特に認知症の予防という観点からは、深い眠りを得られる環境づくりが欠かせません。
快適な睡眠を得るためには、以下のようなことを意識するとよいでしょう。
- 1照明を落として、メラトニンの分泌を促す
- 2就寝1時間前にはスマホを手放し、脳の興奮を鎮める
- 3外部の音を遮断し、静けさを保つことで中途覚醒を防ぐ
また、毎朝決まった時間に起きて朝日を浴びると、体内時計が整い、自然な眠気が夜に訪れやすくなります。
毎日のルーティンに脳トレ時間を設ける
脳の健康を維持するためには、日々の生活に脳を意識的に使う時間を設けることも大切です。特に、ゲーム感覚で取り組める脳トレは、記憶力や判断力を鍛えるうえで効果的とされています。
ただし、重要なのは「楽しい」と感じながら継続することです。たとえば、朝のひとときにクロスワードに挑戦したり、就寝前に新聞を音読したりするなど、習慣の中に無理なく組み込むことで継続しやすくなります。
短時間でも脳にしっかり刺激を与えられる例として、以下のようなトレーニングが挙げられます。
- 1計算練習:おつりを暗算する、簡単な足し算・引き算をする
- 2音読習慣:新聞や書籍を声に出して読む
- 3パズル挑戦:クロスワードやナンプレ、間違い探しに取り組む
これらは、記憶力や集中力の維持、発語機能の刺激、認知機能の強化につながるといわれています。
認知症の種類を正しく知りできることから始めよう

認知症は種類によって症状や進行の仕方が異なるため、それぞれの特徴を正しく理解することが、早期発見と適切な対応の第一歩となります。
また、日常生活の中で脳に良い習慣を取り入れることは、記憶力や集中力の維持、さらにはストレス軽減や心の健康維持にもつながります。
食事や運動、睡眠、脳トレの工夫を日々の生活に取り入れ、できることから実践していきましょう。
さらに、忙しい日々の中で必要な栄養をしっかり補いたい方は、オールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」の活用もご検討ください。
DHA・EPAやプラズマローゲン、葉酸、ビタミンB群など、脳の健康維持に役立つ成分を1日4粒で手軽に補える製品です。将来の備えとして、今日から取り入れてみましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
岩城 裕大
SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
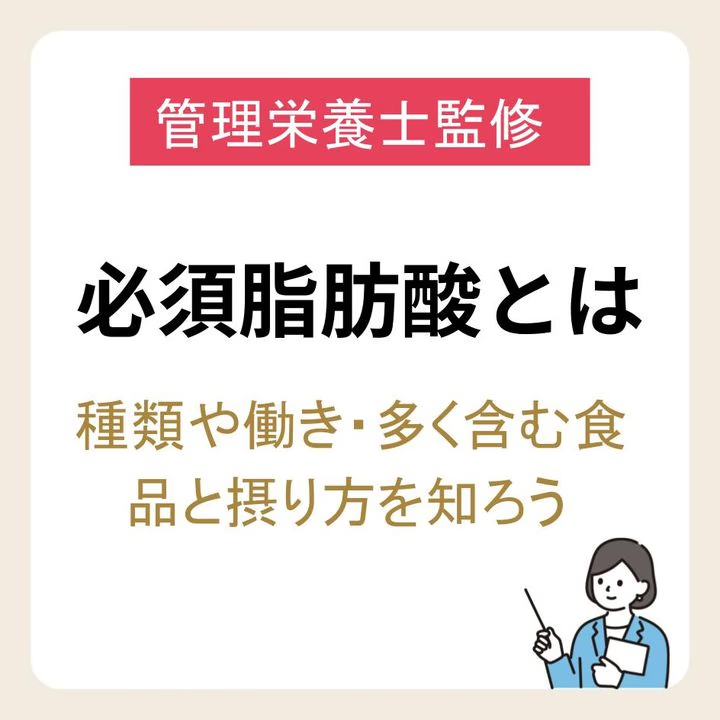
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
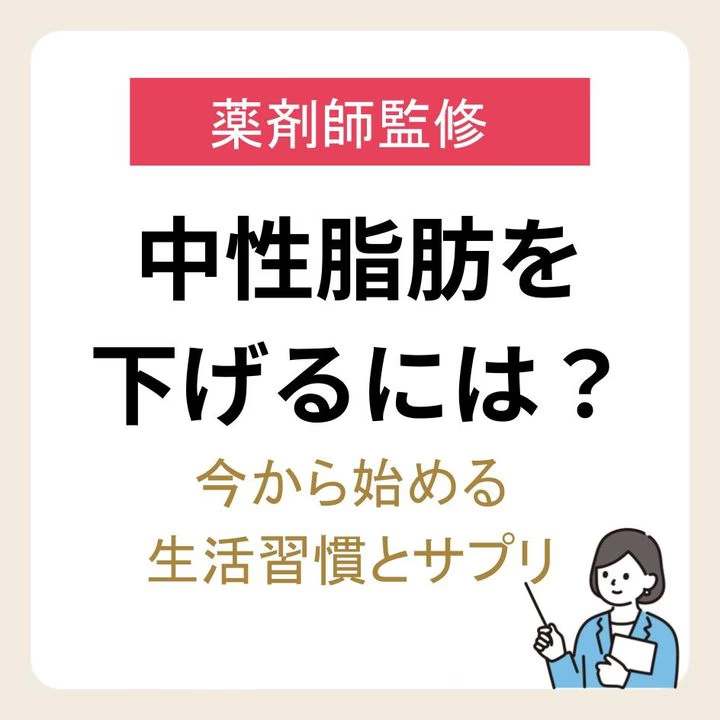
知力健康
【薬剤師監修】中性脂肪を下げるには?今から始める生活習慣とサプリ
健康診断で「中性脂肪がやや高め」と言われたものの、特に体調不良もなく、ついそのまま...